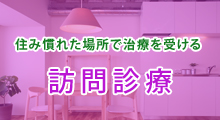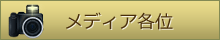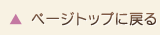歯の食いしばりが引き起こす10の症状と効果的な治療法—放置すると危険!
「気づくと無意識に歯を噛みしめている…」「朝起きると顎が痛い…」
そんな経験はありませんか?歯の食いしばり(クレンチング)は、歯や顎に想像以上のダメージを与えることがあり、放置すると歯の痛み・顎関節症・頭痛・顔の変形など、さまざまなトラブルを引き起こします。
本記事では、食いしばりの症状・原因・治療法を詳しく解説し、改善策をご紹介します。
1. 歯の食いしばりとは?
食いしばりとは、上下の歯を強い力で噛み締めることを指します。通常、歯が接触するのは食事の際の15~20分程度ですが、食いしばりがある方は無意識に1~2時間も続けてしまうことがあります。
食いしばりの主な原因
✅ ストレスや緊張による無意識の習慣
✅ 集中しているときの癖(パソコン作業・運転・スポーツ時など)
✅ 歯の噛み合わせの不調
✅ 睡眠時の無意識の噛み締め(ナイトクレンチング)
自分では気づかないことも多いため、以下の症状に当てはまるかチェックしてみましょう。
2. 歯の食いしばりが引き起こす11の症状
2-1. 噛むと痛い(歯の圧迫痛)
食いしばりによって、歯の周囲にある歯根膜(歯を支える組織)が炎症を起こし、噛むと痛くなることがあります。
2-2. 歯がしみる(知覚過敏)
歯の噛み合わせの面や根元が削れたり、亀裂が入ると歯がしみやすくなります。
2-3. 歯が突然痛くなる(歯の亀裂)
食いしばりが続くと、歯に小さな亀裂が入り、細菌感染によって神経が炎症を起こし、強い痛みにつながることがあります。
2-4. セラミックが割れる
食いしばりが強いと、詰め物や被せ物(特にセラミック)が割れる原因になります。
2-5. 顎が痛い(顎関節症)
食いしばりが続くと、顎関節に負担がかかり、関節円板がずれたり変形したりすることで、顎の痛みや開閉時の異音が発生します。
2-6. 歯が割れる(歯根破折)
特に神経のない歯(治療済みの歯)は脆くなっており、食いしばりによって割れてしまうリスクが高まります。
2-7. 歯茎が痩せる
強い噛む力が歯茎にダメージを与え、歯周病の進行を早めてしまうことがあります。
2-8. 肩こり・首の痛み
顎の筋肉と首・肩の筋肉はつながっているため、食いしばりがあると肩こりや首のこりが慢性化しやすくなります。
2-9. 偏頭痛
頭の側面にある側頭筋が緊張することで、頭痛やこめかみの痛みが発生しやすくなります。
2-10. 顔が大きくなる(咬筋の肥大)
食いしばりが続くと、顎周りの筋肉が発達し、顔の輪郭が角張ってしまうことがあります。
3. 歯の食いしばりの治療法
3-1. 自己暗示療法(意識することが大切)
日中の食いしばりは、「上下の歯を離す」ことを意識するだけでも改善につながります。
3-2. ストレスの発散
ストレスは食いしばりの大きな要因です。運動や趣味、リラクゼーションを取り入れ、ストレスを軽減することが大切です。
3-3. ナイトガード(マウスピース)
寝ている間の食いしばりを軽減するために、ナイトガード(マウスピース)を使用する方法があります。
💰 保険適用で約5,000円程度で作製可能。
3-4. ボツリヌス注射(ボトックス治療)
食いしばりによって発達した筋肉(咬筋)にボツリヌス注射を打つことで、筋肉の緊張を和らげ、食いしばりを軽減します。
⚠ 効果は数か月持続し、定期的な施術が必要です。
4. 子どもの歯の食いしばりも注意!
子どもにも食いしばりが見られることがあり、特に乳歯の時期に強く噛み締めると歯の摩耗や痛みの原因になります。
- 原因は不明なことが多いですが、成長とともに自然に改善するケースもあります。
- 強い痛みが続く場合は、歯科医院で相談しましょう。
5. まとめ
✅ 食いしばりは無意識に行われることが多く、気づかないうちに歯や顎に負担をかけている
✅ 虫歯や歯周病がなくても歯が痛くなることがあり、放置すると歯の割れや顎関節症の原因になる
✅ ナイトガードやボツリヌス注射など、適切な対策を行うことで改善が可能
✅ 自己暗示やストレス解消も食いしばりの予防につながる
「もしかして食いしばっているかも…?」と思ったら、早めに歯科医院で相談し、適切な治療を受けることが大切です。